ブログ
ブログ一覧
梅雨におすすめのケア
今年の梅雨は暑いそうですね。
高温で多湿だと実は「心臓」の負担が増します。
梅雨は湿度が高く、汗が蒸発しにくいため、体に熱がこもりやすくなります。
体は体温を下げようとしてさらに汗をかきますが、水分が失われると血液がドロドロになり、流れが悪くなります。
これにより心臓は血液を全身に送るために負担がかかります。
さらに、体温を逃がすために皮膚の血管が広がると血圧が下がり、1回の拍動で届く血液量が減るので、心臓はより多い回数を動かさなくてはなりません。
心臓が疲れるとむくみやすくなったり、だるさや疲労を感じます。
対策としては、
・睡眠をとる
・暑い時は風を当てて汗の蒸発を促す(目には風を当てない)
・水分を補給する
・軽い運動をして筋肉でのめぐりを促す
があります。
鍼灸では、心臓の反応点を優しくローラーします。
だるさや疲れ、むくみを感じたらぜひ毎日2〜5分ローラーしてみてください。
不整脈や動脈硬化の対策にもなります。
毎日の積み重ねが大切です。
(副)
鍼灸学会@名古屋
2025年5月30日(金)~6月1日(日)第74回全日本鍼灸学会学術大会の名古屋大会が開催され、院長も参加しました。

今大会のテーマは「女性のみかたⅡ―フェムテックによる女性のWell-beingに貢献する鍼灸―」ということで、female(女性)、technology(技術)、Well-being(健康)を追求した学術大会でした。
なお、今大会では、事後参加登録によるアーカイブ配信も可能です。
(一般演題やポスター発表の録画は無いようです。)
詳細は下記のリンクからご確認ください。
■参加登録申込期限:2025年7月22日(火)23:59
■アーカイブ配信期間:2025年6月23日(月)~7月22日(火)※予定
はり灸レンジャーとして、昨年の能登半島地震と豪雨災害の支援について報告させて頂きました。
ポスター発表では、今回のテーマである「女性」についても取り上げました。
被災地では女性の受療者の割合が多いです。
被災者の安心、リスク管理を考える上でも、もっと多くの女性鍼灸師の活躍が望まれます。
発表時には、他の災害支援団体や石川県の先生、災害支援に関心のある学生や先生にもご聴講頂き、発表が終わってからも多くの質問を頂きました。
災害現場で、鍼灸は被災者の支えになります。
が、災害支援に関わる鍼灸師の数はまだまだ少ないです。
いざという時の為に、もっと多くの鍼灸師の先生方にも関心を持っていただければと思います。

(院)
アレルギー対策に腸のケア
3月ですね。
ようやく梅も咲き始め嬉しい反面、花粉が気になる季節です。
花粉症をはじめ、アレルギー症状に腸内環境が関係することは耳にしたことがあるでしょうか?
具体的には腸内細菌が腸内にある腸管免疫を調整し、腸管免疫が腸内細菌のバランスを維持するという仕組みがあります。
腸管免疫(GALT)には、腸内に入ってくる異物(食べ物、細菌、ウイルスなど)を監視し、必要なら攻撃し、有益なもの(食べ物や腸内細菌)は攻撃しない仕組み「経口免疫寛容」があります。
また腸管免疫は必要に応じて抗菌物質(IgA抗体など)を分泌して悪玉菌が増えすぎないよう調整しています。
一方で腸内細菌は以下の物質を出して免疫バランスを調整しています。
〇 短鎖脂肪酸(SCFA)(酪酸・酢酸・プロピオン酸) → 制御性T細胞(Treg)を増やし、炎症を抑える
〇 多糖類(PSA)(バクテロイデス属が産生)→ 免疫細胞を調整し、過剰な免疫反応を抑える
他にも腸内細菌は炎症を起こしやすくする物質も産生します(悪玉菌)。
また悪さをしない「日和見菌」も増えすぎると腸粘膜を傷つけてしまうことがあります。
アレルギー症状の緩和には腸管免疫と腸内細菌の良いバランスが必要そうです。
腸内環境が良ければ、免疫と腸内細菌のバランスも良くなります。
鍼灸は循環を促して腸内環境を改善します。
特に腸粘膜バリアを保つことが大切です。
善玉菌も粘膜を通過して腸外に出てしまうと病原性を持ったり、異物として免疫細胞に感知されたりします。
腸粘膜バリアの改善には血流が必要です。
鍼やお灸の優しい刺激は腸粘膜に血流を促し、修復を促します。
また、腸のぜん動運動を調節し、便秘や下痢も改善します。
発酵食品や食物繊維をとったり、適度な運動も腸内環境を整えます。
腸のケアをプラスして花粉の季節を一緒に乗り切りましよう!
(副)
反応点治療研究会 実技講習会2025年
鍼灸講習会 定期開催による「 学ぶ→ 実践→ さらに学ぶ 」のサイクルで知識・技術習得!
痛みはどのように出現するのか?
内臓疾患に対する鍼灸治療はどのように行えばよいか?
鍼をすると体にどのような神経反射が起こるのか?
など、毎回テーマを変えて2か月に1回、講習会を開催しています。
「鍼灸治療を解剖学・生理学に基づいて紐解いていく」
そんな講習会です。
午前は講義、午後は実技の2本立てで、実技は習得レベルに合わせて学べるので、学生さんや初めての方も安心してご参加いただけます。
【2025年度 日程と各テーマ】
第1回 1月19日(日)<基礎編> 反応点治療とは <応用編> 頭部
第2回 3月9日(日) <基礎編> 反応点とは <応用編> 胸部
第3回 5月11日(日)<基礎編> 痛みの治療 <応用編> 肩背部・上肢
第4回 7月13日(日)<基礎編> 痛みと内臓の関係 <応用編> 腹部
第5回 9月21日(日)<基礎編> 内臓の治療 <応用編> 腰部・下肢
第6回 11月9日(日)<基礎編> 鍼・灸・ローラー鍼の作用 <応用編> 全身・自律神経
午前の部 10:00~11:30 「講義」 午後の部 12:30~15:00 「実技」
【会場】
「講義」<基礎編> 灘区文化センター5階会議室(六甲道勤労市民センター:JR六甲道駅南接)
「講義」<応用編>・「実技」 ミントはり灸院 (JR六甲道駅より徒歩3分)
※ 講義会場は基礎編と応用編で異なります。どちらに来て頂くかは、こちらよりご連絡いたします。
【対象者】
鍼灸師・鍼灸学校の学生
【参加費】
鍼灸師 7,000円 / 学生 5,000円 (午前+午後 1回分の金額です)
【持ち物】
鍼灸道具(普段使っているもの)・スリッパ・筆記用具。
服装は自由、ラフな格好で結構です。
【お申し込み】
反応点治療研究会のホームページからもお申込みいただけます。
https://hannouten.peatix.com/
「講義」だけなら 録画視聴も可能!
午前の講義のみ 録画視聴も可能です
当日参加が無理な方も、録画を後でご覧頂けます。
反応点治療を知りたい方、会場での参加が難しい方、日時の都合が合わない方、下記サイトURLかチラシのQRコードよりお申し込みください。
【オンライン講習費】
鍼灸師2,000円 / 学生1,000円
【お申し込み先】
https://hannouten.peatix.com/
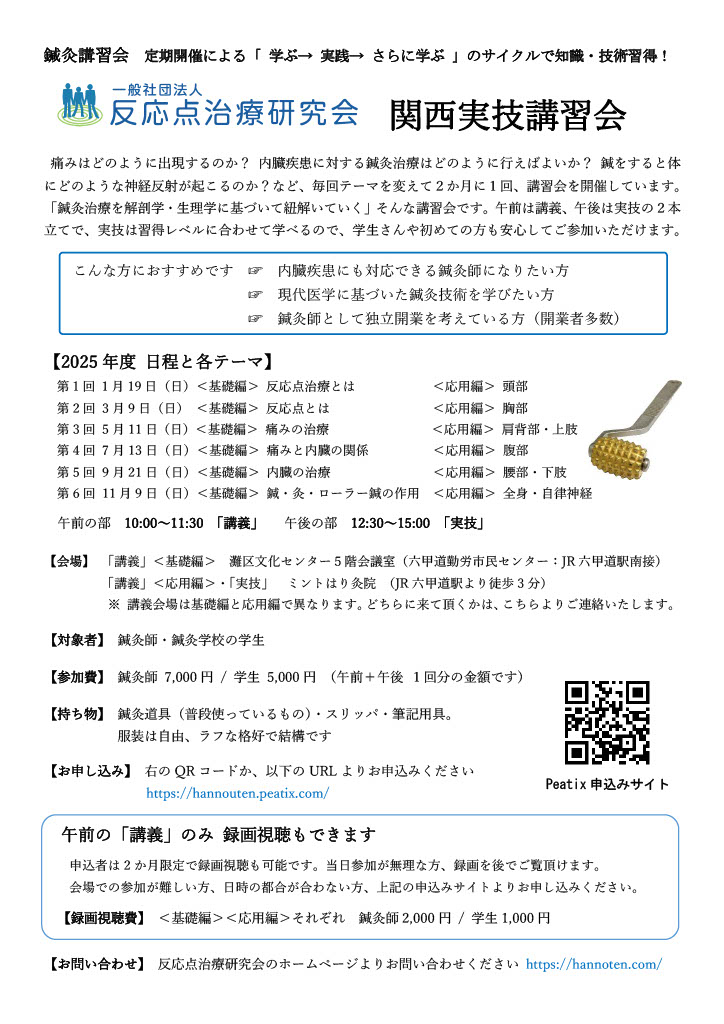
第31回「アレルギー週間」市民公開講座
あけましておめでとうございます。
2025年もどうぞよろしくお願い致します。
年が明けたばかりですが2月に開かれる市民公開講座のお知らせです。
今年も2月20日の「アレルギーの日」が近づきました。
この日にちなんで毎年2月にアレルギーに関する知識や最新の治療についての無料講座が全国で開かれます。
近年は特にアトピー性皮膚炎の治療薬が増え、選択肢が増えています。
一般の方にも分かりやすい内容になっているので、是非参加されてみてください。
関西では
2/2(日)兵庫、
2/8(土)奈良、
2/9(日)滋賀、
2/15(土)京都、
2/16(日)和歌山、
2/22(土)大阪で開催されます。
受講は無料ですが、事前申し込みが必要です。
会場参加、WEBでの参加も選べます。
各会場で内容が違うので、講演内容や申し込みについてなど、詳しくは「日本アレルギー協会 関西支部」HPをご確認ください。